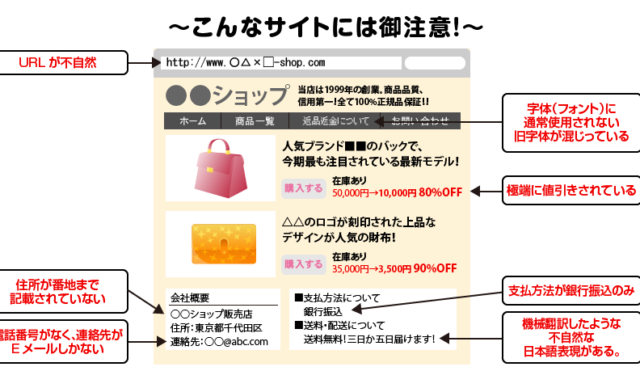先日とあるテレビドラマの切り抜き動画を見ました。
そこで「真実は人の数だけあるけど、事実はひとつ」という言葉が出てきます。
最近育児について考えさせられることが多いので、思うところをまとめてみました。
「親が子のイベントに参加しなかった」という事実
親(特に父親)は仕事を言い訳に、子どものイベントに不参加になりがちです。
「その日は仕事で忙しいから」と、私もつい妻に任せてしまいそうになります。
大事な商談とか、どうしても代わりがいないとか、仕事をしているとそういう時もありますよね。
私もそういう時はあります。
その親にとっては「仕方なかった」で片付く話ですが、渦中の子供はそうはいきません。
ただ「お父さん・お母さんは僕のイベントよりも仕事を優先した」と映るだけ。
このことに、この切り抜き動画を見てはっと気付かされました。
「仕事で忙しかった」というのは単に親にとっての真実(解釈?)でしかなく、
「ただ親が子供のイベントに参加しなかった」という事実は変わらないわけです。
結構大事な視点だと思いました。
以前子どもの参観イベントがあり、人数制限があって妻が行ってくれました。
そのイベントでは、親子で何かレクリエーションをするプログラムが組まれていたそうです。
そこで一人だけ、何らかの事情でご両親が来てくれなかった園児がいました。
一時的に、保育士の先生が親代わりをされていたそうです。
…たぶん、この子はすごく寂しかっただろうし、こういう記憶ってずっと残るんですよね。
子育てを「権利」と捉えるか「義務」と捉えるか
同じ動画の中で、もうひとつすごく考えさせられる言葉が出てきます。
「メジャーリーガーの父親は子どもの成長に立ち会うことを『権利』と思い、日本の解説者たちは『義務』だと思っている」という、強烈な一言です。
要は「やりたくてやっているか」、「(仕方なく)させられているか」という、子育てへの姿勢の違いです。
これ結構大きな差だなーと思いました。
一昔前は「男は仕事、女は育児」という専業的な考えが強かったですね。
今は共働きが当たり前になり、育児も一緒にするご家庭が増えたように思います。
参観日などでこども園に顔を出すと、お父さんが来ているご家庭が驚くほど多いと感じます。
そういえば、男は仕事に専念するのはいいとして、「育児に関わらなくてもいい」って誰が決めたんでしょうね?
大きくなってグレる子供に共通するのは、「家庭に父親の影がない」
何かの記事で読んだのですが、こういう統計データがあるそうです。
もちろん、父親が仕事ばかりしているご家庭のお子さんがすべて、大きくなってからグレるという話ではなく、結果の原因を分析してみたらこうなったという話です。
この記事を読んで、我が子がグレてしまったらどうしよう…とか思ってしまいました。
私が育児に積極的に関わっているのは、「後々後悔したくないから」という理由が大きいです。
こういう統計データ(事実)があるわけですから、もし将来我が子がグレてしまったら、私は一生後悔すると思います。
「あ、この子がこうなったのは自分のせいだ…」と、妻に懺悔しそうです。
何が言いたいかというと
「父親も育児に積極的に関わるべし」とか言いたくなりますが、それぞれのご家庭がそれぞれ異なる事情があるでしょう。
義務感で関わるという姿勢は改めた方がいいかもしれません。
奥さんはうんざりするでしょうが、それ以上に子供がそれを敏感に察知していると思うからですね。
人間何事も前向きに関わることが一番な気がします。